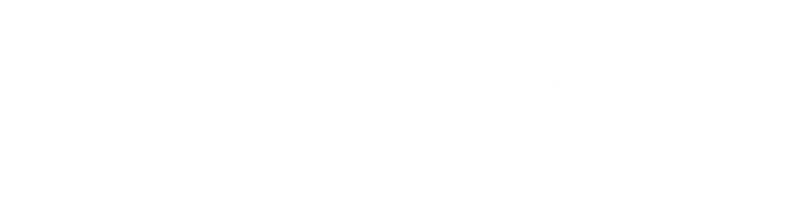GWが暇すぎるから誰かハロメンのエ〇〇な小説書いてほしい
見せたくて暖めてるやつがいるかもしれないと思って立てる側面もある
続けなさい
もももがSNS用にオシャレしたり場所借りたりする資金調達のためにパ〇活に手を出してしまう
そのうちおじさんに上手いことホテルに連れ込まれてしまいそれをネタに更に何度も会うように脅されて
表面上はいやいや会いに行っているが実際はおじさんち○ぽに完堕ちしていて抜け出せないという話がいいかな
—
『朝焼けの予感』
つばきファクトリーのリハーサル終わり、誰もいない控え室に八木栞はひとり残っていた。手には福田真琳と撮った小さなチェキ。お互い変な顔して写ってるのに、それがなぜか一番のお気に入りだった。
「なんで、こんなに気になるんだろ…」
真琳の笑顔。真琳の声。真琳のまっすぐすぎる言葉。全部、胸の奥で静かに波を立てる。
ドアが静かに開いた。
「しおりん、まだいたの?」
福田真琳だった。少し汗ばんだ髪を無造作にまとめて、スポドリ片手にこちらを見る。
「うん…ちょっとだけ、ぼーっとしてた」
「ぼーっと?めずらしいね。いつもちゃきちゃきしてるのに」
冗談まじりに言いながら隣に腰を下ろす真琳。しばらく、2人の間に静けさが流れた。
「ねぇ、しおりん。最近、ちょっと距離とってたでしょ?」
八木はドキッとした。
「そんなことないよ…ただ、なんか、どう接していいか…わかんなくなっただけ」
「どうして?」
「…真琳のこと、好きになっちゃったみたいだから」
福田真琳の目が見開かれる。沈黙。空調の音だけがやけに大きく感じた。
「…やっと言ったね」
「え?」
「わたしも、ずっと言いたかった。しおりんのこと、大好きって。ずっと前から気づいてたけど、言ったら終わっちゃいそうで怖くて」
互いに見つめ合い、小さく笑い合う。赤くなった頬も、照れた視線も、もう隠す必要はなかった。
「じゃあさ、これからは、一緒に…もっと近くにいてもいい?」
「もちろん。しおりんの隣、あたしの特等席だから」
2人の指が、そっと触れ合った。まるで朝焼けが夜を照らすように、静かに始まった恋だった。
—
ご希望に応じて続編や別展開も書けます。さらに甘く?もっと切なく?
スポンサーリンク
甘くいこう
タイトル:「最後の音」
—
放課後の校舎は、いつもより静かだった。教室に忘れ物を取りに戻った福田真琳は、階段を降りる途中でふと耳に届いたピアノの音に足を止めた。
やさしく、けれどどこか寂しげな旋律。――音楽室?
吸い寄せられるようにしてドアを開けると、そこには制服姿の小林萌花がピアノに向かっていた。真琳に気づくことなく、淡々と指を鍵盤に走らせている。
「…ごめん、邪魔しちゃった?」
その声に、萌花はようやく手を止めて振り向いた。
「ううん。誰かに聴いてほしかったのかも」
萌花の声は、音楽よりも少しだけ緊張していた。
「きれいな音だね。その曲…オリジナル?」
「うん。卒業式で流す予定の…まだ誰にも聴かせてなくて」
ふと真琳は、教室で噂になっていた話を思い出した。小林萌花は音大を目指していて、春には遠くの街に行くらしい。
「そっか…じゃあ、もうすぐここで弾くのも最後か」
萌花はうなずいた。そしてぽつりと言った。
「ねえ…真琳は、どうしてここに来たの?」
「なんとなく…でも、今はここに来てよかったって思ってる」
それは、嘘じゃなかった。流れていた音楽も、彼女の表情も、どこかでずっと触れたかった何かだった気がしたから。
萌花が立ち上がり、真琳の手を取った。
「弾いてみる?」
「えっ、私ピアノなんて…」
「大丈夫。最初の鍵盤、いっしょに押すだけでも音になるから」
ふたりの指がそっと並び、静かに音が響いた。たった一音。でも、それはふたりの青春が重なった瞬間の、特別な音だった。
「また…来てもいい?」
「うん。音があれば、私はここにいるから」
校舎に残る夕日が、ふたりの肩を静かに照らしていた。
—
続きが読みたい?それとも別の組み合わせでも書いてみようか?
タイトル:ネカフェの午後、君の横顔
照明を落としたネットカフェの個室に、カチャカチャとキーボードを打つ音が響いていた。八木栞は、顔をしかめながら編集画面とにらめっこしている。
「もう少しで完成なのに…ここのBGMがどうしてもしっくりこない…」
ドリンクバーの紙コップを持った手が、ふと止まる。限られた時間、限られた機材。それでも、動画投稿をやりたくて、ネットカフェに通うようになっていた。
「やぎしー、すごい集中してるじゃん」
突然声がして振り返ると、そこにいたのは小林萌花だった。レッスン帰りのトレーニングウェアに、汗がまだ残っている。
「こ、小林さん!? なんでここに…」
「たまたま近くにいたから入ってみたの。そしたらフロントで“八木栞様ご利用中”って表示見つけちゃって」
くすっと笑うその声に、やぎしーは赤面しながら目を逸らした。
「動画、編集してたの?見せてくれない?」
「…まだ全然、完成してないですし…恥ずかしいです」
「でも頑張ってるやぎしー、見たいな」
そう言って、もふおは椅子の背に手を置いて、画面を覗き込んだ。肩が触れるほどの距離。編集のタイムラインの波形と共に、八木の心臓の鼓動も早まっていく。
「音の入れ方、すごくいいと思うよ。私、音にはちょっとだけうるさいから」
「…ありがとうございます」
「それにしても、やぎしーってさ、こんなに一人で頑張ってるんだね。知らなかった」
「…頑張らないと、小林さんみたいになれないから」
「え?」
「小林さんみたいに、ステージでもちゃんと魅せられる人に、なりたいんです」
一瞬、沈黙が落ちる。だが次の瞬間、小林は微笑みながらこう言った。
「じゃあ、これからもここで編集するときは、私も付き合うよ。レッスン帰りに寄るから」
「…えっ」
「だって、やぎしーのこと、もっと応援したくなっちゃったから」
八木栞はその言葉に言い返す言葉を失い、ただうつむいた。けれどその頬は、ほんのりと桜のように色づいていた。
ネットカフェの小さな個室で、誰にも知られず、ふたりの距離がすこしだけ、近づいた。
?
続きを読みたい?
それから数日、八木栞の動画編集ルーティンに、小林萌花の“寄り道”が加わった。
「今日も来たんですか、小林さん…?」
「うん。やぎしーの集中力が切れないように、ドリンクバーからココアも持ってきたよ。ほら、甘いやつ」
「…ありがとうございます」
ぽつりとした会話、並ぶ椅子、モニターに映る動画の断片。それだけなのに、胸が騒ぐ。八木はそれをごまかすように、編集に集中しようとしたが――
「ねぇ、やぎしーって、私のことどう思ってる?」
その言葉は、予期せぬタイミングで飛び込んできた。
「えっ……」
「いや、変な意味じゃなくて。なんかさ、前より少し仲良くなれた気がしてて」
「……」
八木は、画面の再生を止めた。心の中で、何度も自分に問い直していた気持ち。今、言うべきか、それとも黙って笑うべきか――。
「小林さんは…優しくて、かっこよくて。私にないものをいっぱい持ってて。憧れみたいな、そんな感じです」
「ふーん。じゃあ、やぎしーは私に“憧れられてる”んだ」
「はい…」
「そっか。でも私ね、やぎしーの真っすぐさとか、ちょっと抜けてるとことか、すごく好きだよ」
「……えっ」
「憧れられるのも嬉しいけど、できれば――同じ目線で並んでほしいな」
八木は固まったまま、目を見開いていた。モニターの光に照らされた小林の瞳が、まっすぐにこちらを見ている。
「ね、やぎしー。次の動画、私もちょっとだけ手伝わせて?」
「……はいっ。ぜひ、お願いします…!」
「ふふ。じゃあ、相棒ってことで」
小林が差し出した小指に、八木はおそるおそる自分の指を絡めた。
甘くて、静かで、少しだけ勇気のいる時間が、ふたりのあいだに確かに流れていた。
その夜、ネットカフェの外は春の風。画面の外側でも、ふたりの物語が静かに始まっていた。
――終わり。
ご希望があれば、イラスト風の1シーンも描写しますよ。どうしますか?
—
イラスト風シーン描写:
「約束の小指」
ネットカフェの薄暗い個室。
モニターの淡い光に照らされ、並んで座る二人の横顔。
八木栞は少し頬を赤らめ、驚きと戸惑いが入り混じった瞳で小林萌花を見ている。
小林萌花は、やさしい微笑みを浮かべながら、まっすぐな視線で八木を見つめ、小指をそっと差し出している。
その手は細くて繊細で、でも何かを導こうとするように、少しだけ強い。
やぎしーの手が、ためらいながらもその小指に触れ――
二人の小指が、静かに、やわらかく結ばれる瞬間。
背景には編集ソフトの画面、タイムラインが流れたまま止まっている。
それでも今、時間は確かに「ふたりのためだけに」動いていた――。
—
このシーンをアニメ風イラストにして描くこともできます。ご希望ですか?
引用元:https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1746167302